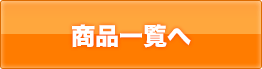第2回 肺で呼吸するとは・・・どういうこと?
第1回では、人間の最も重要な臓器である心臓についてお話させて頂きました。
心臓と同じように大切な臓器として、肺が挙げられます。
肺は呼吸をつかさどっており、全身に酸素を送るのに役立っています。
さて、この肺ですが、一体どのような構造になっているのでしょうか?
肺のことを理解するためには、まずはその解剖を知ることが非常に大切です。
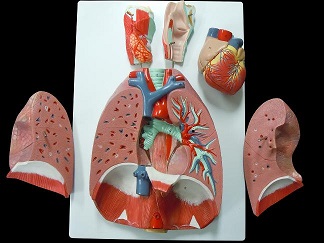
左の写真が、肺と心臓の位置関係です。
真ん中のくぼんでいる部分に心臓があり、心臓からは2つの大きな血管が出ていきます。
赤い方が大動脈、青い方が肺動脈です。
血管の赤い、青いは、「酸素がどれくらい含まれているか?」を表しています。
全身に向かう赤い血管・・・「大動脈」は酸素が豊富に含まれている血液が流れています。
これに対して、肺に向かう青い血管・・・「肺動脈」には、酸素がほとんど含まれていません。
酸素がほとんど含まれていない血液が肺に向かい、肺の中でたっぷりと酸素を蓄え、心臓にもどってきます。

「肺に流れた血液が、酸素を蓄え、心臓にもどる」ということに関しては、左の図を見て頂ければ分かりやすいと思います。
青い血管が肺に入っていく血管、赤い血管が肺から出ていく血管です。
(水色のものは、「気管支」です。)
目には見えませんが、青い血管がどんどんと枝分かれしていき、毛細血管になっていきます。
また、気管支もどんどん枝分かれして、肺胞という組織につながります。
さて、私達が息を吸うと、その空気は気管に入り、気管支へと枝分かれし、最終的に肺胞に入っていきます。
そして、この空気が肺胞で毛細血管(肺動脈が枝分かれした場所)に入っていきます。
空気がたくさん蓄えられた血液は、肺胞を出ていき、合流し、肺静脈になります。
「肺胞に入った空気が、毛細血管に入っていく」と言われても、実際にその様子はイメージが湧かないかと思います。
そこで、以下のような写真を見て頂くと、分かりやすいかと思います。
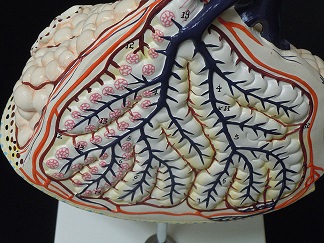
この写真のピンクの丸いものが「肺胞」という組織です。
ピンクの丸に注目してもらうと、そこには青い血管が入ってきており、赤い血管として出て行っている様子が分かります。
これが、「肺胞で酸素を蓄え、肺静脈になっていく」という過程の拡大像です。
人間の体には、このような「肺胞」が約5億個あると言われ、肺胞の面積は全て合わせると100平方メートルとなります。
これは、「10m×10m」の敷地に相当し、畳50畳くらいです。
体の中にここまでの空間が用意されているというのには、驚きますね。
次に、呼吸に関して知っておきたいことがあります。
それは、「そもそも私たちは、どうやって肺を動かすのか?」ということについてです。
(肺には筋肉が無いので、自分で動かすことはできません。)
そのヒントは、下の写真に隠されています。
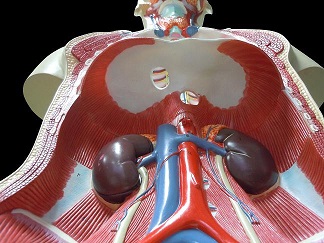
左の写真は、腹部の内臓を全て取り除き、下から眺めたものです。
お腹の真ん中くらいに、筋肉のようなものがあるのを観察して頂けることでしょう。
これが、「横隔膜」です。
呼吸をするときには、横隔膜が下にさがります。
それに伴って、肺が広がり、肺の中に空気が入っていきます。
ちなみに余談になりますが、横隔膜は焼き肉で言えば、「ハラミ」です。
その名前の通り、お腹の中にある筋肉なのです。
以上、肺の構造や呼吸という現象についてお話させて頂きました。
肺は心臓と密接に関っていますから、「心臓の解剖」のページも合わせて読んで頂くことで、より一層理解が深まるのではないかと思います。
最後に、肺はどんな感じで膨らむのか・・・
以下の映像を通して見て頂くことができます。肺という臓器を体感して頂ければ幸いです。
次回:
第3回 人間の体の司令塔・・・「神秘の脳」
※参考
第2回 「肺で呼吸するとは・・・どういうこと?」で説明に用いた人体模型は・・・
・実物大精密肺模型・・・胸部の内臓を1枚のプレートに再現した模型です。
・デラックス 肺組織拡大模型・・・肺を顕微鏡で見た構造を再現した模型です。
・アルティメットEX・・・全身の内臓を再現した等身大のトルソーです。