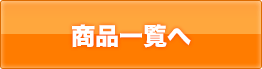第4回 「食べたものは胃で吸収される」・・・これは間違い!
子供さんが興味を持つことで多いのは、「食べたものはどこに行くの?」ということです。
科学館などに言っても、消化管をモチーフにしたトンネルのようなオブジェを頻繁に見かけます。
そこで、第4回である今回は、「胃は何をしているのか?」ということについてお話させて頂きたいと思います。
よくある勘違いに、「食べたものは胃で吸収される」と思っておられる方がおられますが、実はそんなことはありません。
食べたものが吸収されるのは小腸という臓器で、胃は吸収の前の段階の消化を行っています。
食べたものは口から入り、食道を通過し、胃に入ります。
つまり、食べ物が最初に入る臓器が胃ということになります。
以下の写真を参考にしてみて下さい。
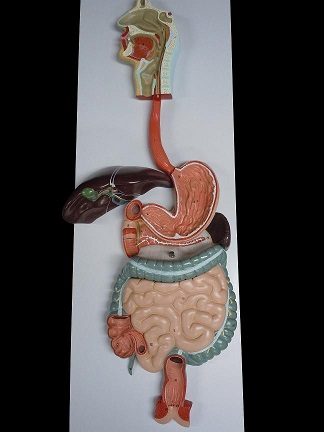
左の写真は、消化管全体を人体模型で再現しています。
口から入った食べ物は、「胃→十二指腸→小腸→大腸→肛門」と移動し、便として排出されます。
前半の方では消化液と混じり、食べ物が吸収されやすい形へと変わっていきます。
そして小腸以降では、様々な栄養素が吸収され、体内へと取り込まれていきます。
胃からは胃液が、肝臓からは胆汁が、膵臓からは膵液が分泌され、それぞれの過程で栄養素が分解されます。
ただし、「アルコール」だけは胃で吸収されます。
お酒を飲んですぐに酔ってしまうことがあるのは、「飲んですぐにたどり着いた胃で、いきなり吸収される」からです。
それでは、次に胃の外側を見てみましょう。
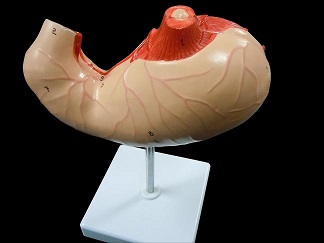
左の写真は、実物大の胃の人体模型です。
胃の容積は約100ccですが、膨らむと約2Lまで大きくなります。
空腹時の時の胃の大きさは、「握りこぶし1個分」と、意外と小さいものです。
胃を外から見ると、「袋」のように見えますが、実は3層の筋肉から構成されています。
胃の主な役割は、肉類などに含まれている「たんぱく質」を分解することです。
胃の壁からは胃酸という強い酸が分泌され、3層の筋肉で攪拌しながら肉などを溶かしていきます。
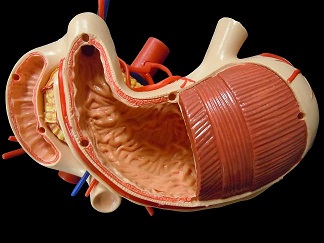
左の写真は、胃の壁の筋肉の様子を表しています。
外側から順に、縦走筋、輪走筋、斜走筋の3層になっており、それぞれが縦、横、斜めに動き、胃の中の食べ物を混ぜ合わせます。
その結果、食べ物と胃液が混ざりあい、粥状になるまで分解されていきます。
たんぱく質を分解するための胃酸・・・非常に強い酸である、「塩酸」が含まれています。
塩酸のPHは、1~2.5前後ですから、皮膚に付着するとただれてしまうほどです。
また、胃液には塩酸以外にも、ペプシノーゲンという消化酵素が含まれており、たんぱく質を分解するのに役立ちます。
さて、このようなお話をすると、「なぜ強い胃酸が出ているのに、胃は自分自身が消化されないのか?」と疑問に思われる方もおられます。
その秘密は、胃液に含まれる粘液にあります。
胃液には「粘液」が含まれており、胃液から胃をブロックしているのです。
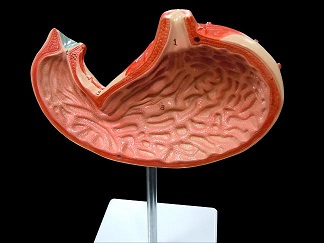
左の写真は、胃の内側を再現したものです。
胃の内側には「ひだ」がたくさんあり、そのひだのなかに、胃腺という胃酸を分泌する部分があります。
胃液は1日に約2L分泌され、食べ物の消化を行っています。
このように、胃ではたんぱく質を消化し、体に取り込みやすい形に変えています。
「食べ物は胃で吸収される」「胃では何でも消化される」というのは、大きな勘違いです。
胃で消化された食べ物は、十二指腸へと流れていきます。
十二指腸では、膵液や胆汁と混ざり、さらに吸収しやすい形へと変わっていきます。
このあたりの様子については、次回以降の記事でご紹介させて頂きますので、楽しみにしておいて下さい。
次回・・・
第5回 1500gの巨大臓器・・・「肝臓」の役割
※参考
第4回 「食べたものは胃で吸収される」・・・これは間違い!で用いた人体模型は・・・
実物大胃模型・・・胃を実物大で再現した模型です。
胃、十二指腸、膵臓模型・・・胃と周囲の消化管を再現した分かりやすい模型です。
消化管全体 実物大模型・・・口から肛門まで、全ての消化管を、実物大で再現した分かりやすい模型です。